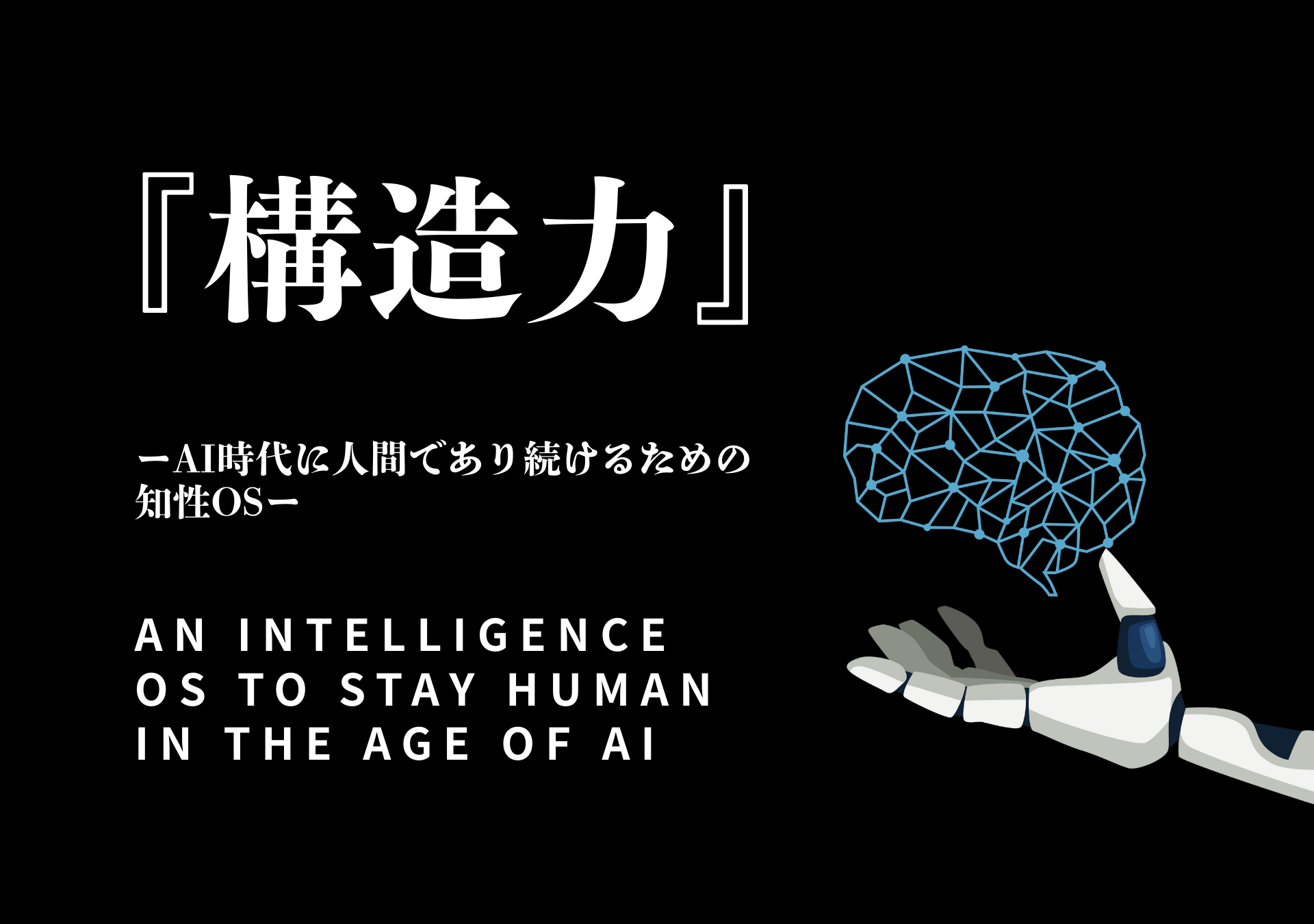1-4. 構造力の衰退──数字社会に奪われた設計の力
今、社会全体が「構造を見る力」を急速に失いつつある──にもかかわらず、それに気づいている人は驚くほど少ない。ビジネスでは、DXやデータドリブン経営が正義とされ、「数字さえ見ていれば正解にたどり着ける」といった幻想が蔓延している。あらゆる現場で、ダッシュボード、KPI、グラフが意思決定の“中心”に置かれるようになった。 だが、それらはすべて“結果”にすぎない。本来、数字は「意味のある構造」の果てに生まれる“現象”であり、構造の代替にはならない。 本来、問うべきは「今の目的に対して、何を可視化すべきか?」「こ ...
1-3. 未来における“設計”と“予測”の重要性
これからの時代、「未来を読む力」以上に、「未来を設計する力」が問われるようになる。未来は、待つものではなく、つくるものだ。にもかかわらず、多くの人が「未来予測」に依存しすぎている。 AIや専門家の意見に頼って、「これからどうなるか?」を知ろうとする。しかし、予測とはあくまで“現在の延長線上”の話にすぎない。想定外の変化が日常になる現代において、予測がいかに不確実なものかは、誰の目にも明らかである。 では、どうすればいいのか。答えは明確だ。「未来を予測する側」ではなく、「未来を設計する側」にまわること。そし ...
1-2. ChatGPTが十分発達した時代に人間が果たすべき役割
近い将来、ChatGPTの最上位プランに加入すると、AGI(汎用人工知能)を搭載した人型ロボットが自宅に届くようになる──そんな時代がもう手の届くところまで来ている。 彼らは、曖昧な指示を即座に理解し、家事・調査・資料作成からプレゼン代行、さらには他者との交渉や顧客対応まで、完璧にこなしてくれるだろう。職場にも家庭にも「最強の右腕」が常駐することが当たり前になる。 このような世界において、もはや「能力のある人」が活躍するのではない。「自分で動ける人」や「行動が速い人」では差別化できない。では、何が人間の価 ...
第1章:なぜ今「構造力」なのか?|1-1. 実行力の価値が下がる時代
かつて「実行力」は、最も価値あるスキルの一つであった。どれだけ多く行動できるか、どれだけ早くPDCAを回せるか、どれだけ泥臭く動けるか──それが成果を分ける明確な指標だったのである。 しかし今、その価値は確実に変わり始めている。AIが指示通りに正確かつ高速に動けるようになった時代において、かつて「実行力」と呼ばれていた領域は、機械やアルゴリズムによって代替可能になってきた。 例えば、情報収集や文章生成、仮説構築や分析、アイデアのブレインストーミングまで、以前なら人間の手で「汗をかきながら」こなしていたこれ ...
-e1754225260903.png)